地球上にはそれぞれの地域で独自に発展してきた民族音楽が数多く存在するのに、なぜクラシック音楽を含む広義の「西洋音楽」だけが一種の業界スタンダードになったのでしょうか? その要因はいろいろあると思いますが、なんといっても「楽譜」と「記譜法」の発明がいちばん大きいのではないでしょうか。人間の言語には「ことばのカベ」が厳然と存在しますが、楽譜は世界中のだれもがその楽曲をすぐ演奏できるようにする、万国共通の指示書きのようなものだからです。
今回は、クラシック音楽をクラシックたらしめている「楽譜」について、とくに「記譜法」と楽譜作成に欠かせない「道具」を中心としたよもやま話の前編です。
「記譜法」の発明者、グイード・ダレッツォ
小学校に入って、最初の音楽の授業でなにを習うかと言えば、「ド・レ・ミ…」と声に出して歌うことではないでしょうか。さてこのドレミ唱法、起源はけっこう古くて、中世北イタリアの都市国家のひとつアレッツォの大聖堂で聖歌隊を指導していたグイード・ダレッツォ(992、995頃-1050頃)というベネディクト会修道士の考案した方式にさかのぼります。
グイード師は当時、「グレゴリオ聖歌」の指導に行き詰まっていたようで、何百もあるレパートリーをなんとかして聖歌隊員におぼえこませようと苦心惨憺。そこで彼が考え出したのは『聖ヨハネ賛歌』を利用して高さの異なるそれぞれの音に名前をつけ、旋律を歌えるようにしよう! という斬新な解決法でした。
この聖歌、第1節から第6節までの最初の音がそれぞれ日本式の階名で言えばハ-ニ-ホ-ヘ-ト-イの6音[ヘクサコード]と一致するという、音階学習にはまさにうってつけの曲で、ここに各節冒頭語句の最初の音をそのまま当てはめ「ウト―レ―ミ―ファ-ソ-ラ」としたのです。アイディアマンのグイード師の発明はそれだけではありません。彼は歌詞の上に赤い横線を引き、その音の高さを「ファ」と決めました。これは7音からなる全音階に含まれるふたつの半音への注意を促すための工夫であり、のちにこの赤線付きの音は「へ音記号」へ、そしてもうひとつの半音、「シ-ド」を表す黄色の二本目の線のほうはのちに「ハ音記号」へと発展したと言われています。(当初「ウト」と表記されていた音は、その後いまの「ド」へと変化します)。

このように11世紀には半音注意! を知らせる「ファ」と「ド」を示す二本線のみだった楽譜も、その後もっと横線があったほうが便利だよね、となって、13世紀になると「五線譜」が登場します。その後しばらくのあいだ、とくにイタリアではネウマと呼ばれる四線譜、五線譜、そして六線譜まで共存していました。
グイード師が聖歌隊にレパートリーを覚えやすくするために編み出した「発明」は、その後の西洋音楽の流れを劇的に転換することになります。それまで音楽はもっぱら歌い手たちの口伝えで一曲一曲、「記憶して」ゆく職人芸で、「人が記憶しないかぎり、どんな音も消える(『語源論』の著者聖イシドールのことば)」しかなかった芸術。そこにグイード師が「紙に曲を書き留める人」、つまり作曲家の出現への道をはからずも開いた、というわけです。彼がこの発明をしていなかったら、ヨーロッパ音楽はバッハもモーツァルトもベートーヴェンも輩出しなかったかもしれず、「音楽の世界標準」的な高みにまで到達することもなかったでしょう。
なお、ときおり引き合いに出される「グイードの手」という音階の早見表は、彼の代表的著作の『音楽小論(なんと、春秋社から日本語版も出ています!)』にも言及されていないことから、もっとあとの時代に考案されたもののようです。
『聖ヨハネ賛歌』
楽器演奏のためのタブラチュアと「数字付き低音」の時代
ところで教会の聖歌隊がグレゴリオ聖歌などを歌う場合に使用されたのは四線譜のネウマで、おもに「音の高さ」を視覚的にわかるようにした、声楽のための楽譜とでも言うべき記譜法。では当時、発展段階にあったリュートなどの弦楽器やオルガンなどの鍵盤楽器のための楽譜にはどのようなものがあったのでしょうか?
もっとも普及していたのが「書字板」を意味するラテン語に由来する「タブラチュア」という、暗号みたいな文字譜と呼ばれる記譜方式の一種でした(「現存最古の楽譜」はエジプトで出土した「オクシリンコス・パピルス」に記された3世紀後半の独唱聖歌「三位一体の聖歌」の断片と言われ、これもギリシャ記譜法という古い文字譜で書かれています)。とくにドイツでは「オルガン・タブラチュア」がさかんに使われており、中部ドイツのハレで教会オルガン奏者をつとめていたザムエル・シャイトはそれに代わる近代的な五線譜で書いた3巻からなるオルガン曲集を出版したさい、そのタイトルをわざわざ『新譜表[Taburatura nova]』と名付けたほど。ドイツもタブラチュアで書いてる場合じゃない、これからはイタリア式の五線譜の時代なんだ! と、五線譜黄金時代の到来を高らかに宣言したかのようなタイトルです。
このタブラチュア、五線譜による記譜法が完成したあとも姿かたちを変えて使われつづけ、現在もギター弾きにはおなじみの「TAB譜」となっていまなお生きつづけています。

もうひとつ数字の入った楽譜というものがありました。それが「数字付き低音」、つまり通奏低音譜です。通奏低音はバロック音楽の作曲家にとっては曲作りの根幹であり、そのためかバロック音楽の時代は別名「通奏低音の時代」と呼ばれたりもします。
通奏低音譜というのはおもにリュートやチェンバロ、オルガンといった、左手は記譜されたベースラインを、空いている右手で音程を示す数字を頼りに楽譜には書かれていない和音もしくは和音を含むパッセージをバラバラと即興的に追加するという離れ業を要求する、かなり高度なテクニックであります。モダンジャズのコード進行も、部分的には通奏低音の進行と類似しています(通奏低音の具体的な演奏法についてはWikipediaの「数字付き低音」を参照)。
ザムエル・シャイト / オルガン曲集『新譜表』から「第9旋法によるマニフィカト SSWV 148」[演奏:マーティン・リュッカー]
バッハ『フルートと通奏低音のためのソナタ ホ短調 BWV 1034』から「アンダンテ」
[演奏:フルート / ルイス・ベドシ、チェンバロ / ロバート・ヒル]
バッハ大立ち回り事件の影に作曲家の七つ道具あり
さて通奏低音でもなんでも弾きこなしたというバロックの天才バッハですが、バッハ好きのあいだでつとに有名なこぼれ話があります。それが、アルンシュタットという町の教会オルガン奏者だった青年バッハと、そこの教会でバッハが指導していた聖歌隊に所属していた「禿げ頭のバッハ」ことガイヤースバッハとのチャンバラ事件。
1705年8月4日の夜、町の中心部の広場にさしかかったときに呼び止められ、振り返りざまにそいつに一発、お見舞いされたわれらがバッハ青年。若気の至りとはこのことか、バッハは携行していた「短剣」をさっと抜いて相手に斬りかかったという、なんか「松の廊下」のような立ち回り事件です。
そこで思うのが、なんでバッハはナイフ、あるいは短剣というぶっそうなものを持ち歩いていたのか? ということ。当時のドイツの田舎町はニューヨークなみに危険だったのか?
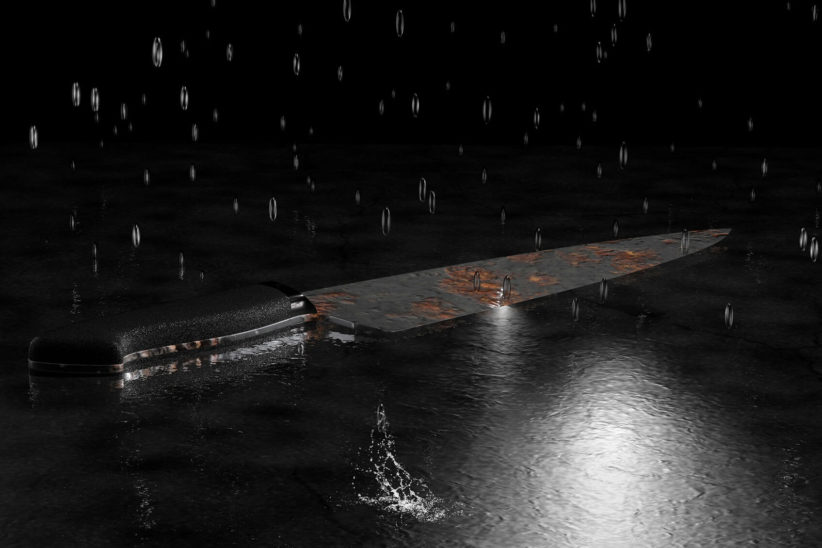
じつはそうではなくて、ナイフはこの時代の作曲家にとっては必需品。当時の手漉きの紙はいまよりはるかに厚みがあり、書き損じの訂正を入れる余白もない場合、高価な紙の節約も兼ねてナイフで表面をこそぎ落として上書きしていたのです。もちろん当時の書き道具は「羽ペン」だったので、先の丸くなったペン先を削るため、という理由もありました(金属のペン先もなかったわけではありませんが、符頭を塗りつぶすのに不向きだったため、弾力性のある羽ペンが一般的でした)。現代の作曲家は原稿用紙のように「印刷された五線紙」がかんたんに買えますが、当時はもちろんそんなものはないので、「ラストラール」という熊手のような専用の道具で作曲家みずから手漉きの用紙に五線を引き引きして楽譜を自作おりました。
ちなみにバッハの『フーガの技法 BWV 1080』の、自分の名前BACHを3番目のフーガ主題として刻んだ最終フーガには、ドイツ式のオルガンタブラチュアで訂正を入れた個所が含まれています。タブラチュアで訂正を書いた理由は、通常の記譜方式では不可能なせまい余白にもしっかり記譜できる利点にあったと思われます。1750年ごろの音楽家で、オルガン用のタブラチュアが不自由なく読み書きできたのは、バッハが最後だったかもしれません(→ 「Bach Cantatas Website」には1982年に発見された、青年時代のバッハのオルガン作品『幻想曲 ハ短調 BWV 1121』の自筆タブラチュア譜画像が見られます)。

【楽器は?配列は?】バッハ『フーガの技法』を聴く技法 【わかんないことだらけ】
というわけで、「クラシック音楽・楽譜の迷宮へようこそ / 後編」へとつづきます。


