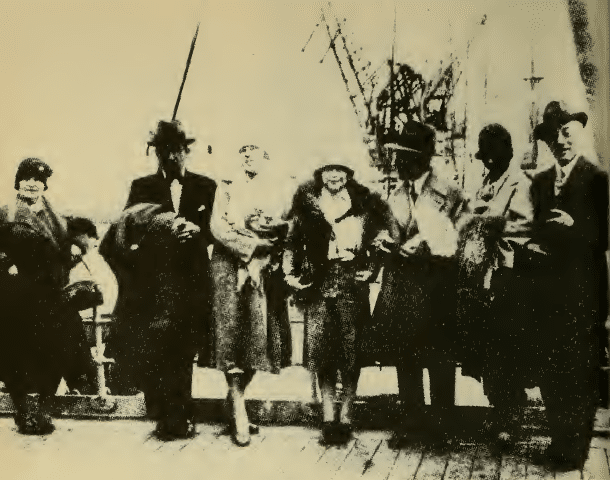⇒前回の記事(モーリス・ラヴェルのアメリカツアー(1)【歓迎! 熱狂! 波乱と至福の4ヶ月】)
音楽著作権を扱うフランスのSACEMは、1992年8月の時点で、フランスにおける印税の最高取得者は、モーリス・ラヴェルであると発表しました。ポップスやロック、映画音楽の作曲家も含めた中のトップとのこと。ということは『シェルブールの雨傘』などで知られるミシェル・ルグランやポップスのセルジュ・ゲンスブール、ポール・モーリアより売れた、ということになるのでしょうか。
さてラヴェルのアメリカツアーの第2回目は、クリーブランド以降の旅の話です。1月21日にシカゴでのコンサートを終えたラヴェル一行は、翌22日にクリーブランドに到着。その日の午後、クリーブランド美術館でレクチャー+コンサートを開きます。ラヴェルのレクチャー? そうです、アメリカツアーの中で、ラヴェルはコンサートの前に何回か、現代音楽についてのレクチャーを行なっています。内容については、この記事の文末にて紹介します。
6. リハーサルの珍事:音楽監督ソコロフ vs. ラヴェル
オハイオ州クリーブランド。1月26日、27日はメソニック・ホールでクリーブランド管弦楽団との共演が予定されていました。当時、音楽監督を務めていたニコライ・ソコロフ(1886年 – 1965年)が、ラヴェルについて興味深い思い出話を語っています。(この二人、性格が合わないのか、ソコロフの表現はかなり辛らつです)

この2日間の演目は『クープランの墓』『高雅で感傷的なワルツ』『スペイン狂詩曲』『シェヘラザード』『マ・メール・ロワ(マザーグース)』『ラ・ヴァルス』の全6楽曲。ソプラノのリサ・ローマが賛助出演しています。プログラムを見ると、クリーブランド管弦楽団の公式ピアノはスタインウェイであるが、リサ・ローマはメイソン・アンド・ハムリンのピアノを使用すると書いてあります。これは前回書いた、ツアー中の使用楽器に関する契約のためでしょう。
コンサート当日の朝10時前、音楽監督のソコロフは、リハーサルスタジオでスタンバイしてラヴェルの到着を待っていました。彼は前日に、第一バイオリンのカールトン・クーリーに、ラヴェルが泊まっているスタットラー・ホテルに寄って、「リハーサルにお連れするよう」頼んでいました。ところが約束の10時になってもラヴェルもクーリーも姿を現しません。オケをいつまでも待たせておくわけにいかないので、ソコロフはリハーサルをはじめます。彼はクリーブランド管弦楽団創立時以来の常任指揮者でもありました。
10時20分になってやっと二人が現れます。ラヴェルはなんだかソワソワとした様子です。リハーサルが始まっているのを目にして、ラヴェルはひどく驚きます。自分がいないのにどうして?! ソコロフは、アメリカではオーケストラを待たせて時間を無駄にすることはできない、と説明します。「おや知らなかったなぁ。フランスではそれほど几帳面ではないんでね」とラヴェルが返しました。するとソコロフは、リハーサル時間の1分1秒が貴重なんですよ、と繰り返しました。「はいはい、わかりましたよ。明日はちゃんと来るようにしましょう」(遅れたのにはラヴェルなりの理由があったのです。)
さてリハーサルがやっとはじまりました。ラヴェルは首がとても長く頭も大きいけれど、背がとびぬけて小さいため、後ろの方の楽団員からは姿が見えにくい、さらには指揮の仕方がかなり変わっていました。まず指揮棒はつかいません。指先をくっつけてヘビの頭のような形に固め、それをユラユラとくねらせるのです。楽団員はラヴェルがいったい何を指示しているのかわからず困った、とソコロフは言います。
すると練習の最中、突然ラヴェルが声をあげました。「いやちがう、ちがう、ちがう、それでは遅すぎる」
ラヴェルが指揮の途中で手をゆるめるので、オーケストラがテンポを落とすのです。「じゃあ、あなたがテンポをゆるめずにドンドンやってくださいよ、そうすりゃみんなついていきますから」またラヴェルがオーケストラの楽器の位置を把握していないことにも驚いたといいます。この人は自分の指揮能力のなさにまったく気づいてない、とソコロフはリハーサルを経て、思ったそうです。
ソコロフは、その晩のコンサートのことは忘れることができない、と語っています。ほとんどノイローゼになりそうだったと。というのもラヴェルはオケの楽器の位置を把握していないため、あらぬ方向を見て指揮をしていたというのです。『スペイン狂詩曲』のときには、ビオラのところでチェロの方を向いてしまったり、パーカッションのとどろきが始まる箇所では、ラヴェルが違う方向を見ていたため、ゆるーい入りになってしまったなど。でも聴衆たちは、「素晴らしい楽曲を生み出した、作曲家としてのラヴェル」の偉業をたたえ、コンサートは大成功に終わりました。ただし、ソコロフは「ラヴェルとの共演はこれが最初で最後だ」と思ったそうです。
この日のコンサートについて、評論家たちは耳馴染みのない新しい楽曲に対して、「情緒がない」「息が短い」「奇異だ」「無味乾燥に聞こえる」など当惑ぎみの感想をもらしました。ただし楽曲のオーケストレーションには舌を巻いたそうです。一方ラヴェルの方はといえば、クリーブランド管弦楽団に強い印象をもったようです。どこよりも素晴らしいオーケストラだ、その要因はメンバーの国際性にあるのではないか、と語りました。中でも金管楽器は楽器そのものの良さに加えて、演奏者がドイツ人で、深く豊かな音を出し、そのレベルは非常に高い、と評価しました。(ちなみに、彼曰く、木管楽器についてはフランス人演奏家が世界一だそうです。)
ところで、1日目のリハーサルにラヴェルが遅れた理由です。これがまた奇妙な、でも一風変わったラヴェルらしいものでした。ホテルまで迎えに行った第一バイオリンのクーリーがドアの前で名前をつげると、部屋の中から「入ってくれ」と声がしました。中に入ると、鏡の前でラヴェルが頭に手をやり、パニック状態に陥っていました。ラヴェルは髪が乱れないようにするため、ベッドに入るときヘアネットをかぶる習慣がありました。それが髪にからみついて取れなくなっていました。しかもラヴェルはひどい近眼のため(ソコロフの想像では、いい格好しいのため眼鏡をかけていない)、それをうまく解きほぐすことができずに格闘していた、というわけです。からみついたヘアネットは、クーリーが手を貸しても外すのが大変だったくらい、収拾のつかない状態でした。
7. にんじん少年とラヴェル
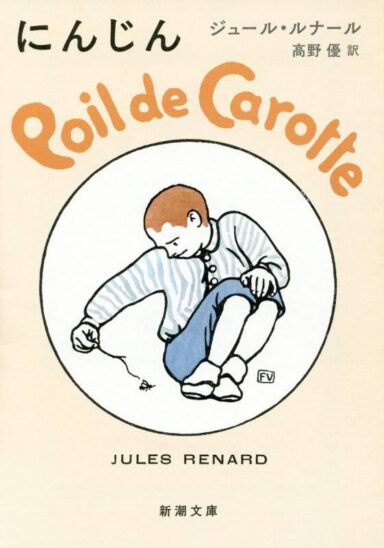
『にんじん』(新潮文庫版):表紙のイラストはフランス版と同じフェリックス・ヴァロットンによるもの。
クリーブランドではラヴェルにとって、ちょっとした心ときめく出会いがありました。作曲を学ぶ赤毛の少年デイヴィッド・ダイアモンド君、13歳。コンサートのあと、燕尾服のままのラヴェルと初めて会ったときのことをよく覚えている、鋭い顔つきで彫像のようだった、と少年は語っています。
ダイアモンド君はフランス語を少し話し、鮮やかな赤毛の持ち主でした。そして13歳でしたが、ラヴェルより少しだけ背が高かったといいます。ラヴェルは少年を紹介されるとその顔をじっと見つめ、ニコッと笑って「君はにんじんだ!」と声をあげました。「にんじん」とはジュール・ルナールの小説『にんじん』(原題はPoil de carotte=人参の毛=赤毛)のことです。
ラヴェルは少年の着ていたパープルのタートルネックに手を触れると、「トレボー(きれいだね)」と言い、燃えるような赤毛に指をサッと通しました。ダイアモンド君が自作の曲を見せると、めんどりが鳴くような声で「オッ、オッ、オッ」と叫び、少年につきそって来ていた音楽教師に、明日ホテルまでこの子を連れてきなさい、と告げました。
翌日、ダイアモンド君は音楽教師に連れられて、ラヴェルのホテルを訪ねます。後に、そのときの印象を「歩く虹」のような人だった、と語っています。白い頭髪にオレンジのジャケット、中にはパープルのシャツを着て、鮮やかな青いネクタイ、深緑のズボンにツートンカラーのゴルフシューズ、と輝くばかりにドレスアップしていたのだとか。そのラヴェルが少年を部屋に迎え、引き寄せて抱きしめたとき、ダイアモンド君はこの人はぼくのことが好きなんだ、と感じたといいます。
ダイアモンド君は8歳の頃から、自分が男の子に惹かれることに気づいていました。ラヴェルは両頬にキスをし、少年の首筋にも唇をあてました。ダイアモンド君は天にも昇る心地でした。大人になってからフランスに留学したダイアモンド君は、作家のアンドレ・ジッド(1869年 – 1951年)と親しくなり、少年時代にラヴェルと会ったことを伝えると、ジッドは興味をそそられたようでした。出会いのときキスを受けたことに触れると、「どこに? いつ?」とジッドは興奮気味に問いただしたといいます。「あの人はぼくのことがすごく好きなんだ、と感じました」とダイアモンド君が告げると、ジッドは「そうかい、うん、そりゃよかった」と頷きました。ジッドは以前からラヴェルの性的嗜好に興味を抱いていたようです。ジッド自身、自分が同性愛者であることを自伝『一粒の麦もし死なずば』で公表しています。
ラヴェルは少年とホテルで会ったとき、ナディア・ブーランジェ(フランスの作曲家、音楽教師。1887年 – 1979年。ホロヴィッツ、バーンスタインなど20世紀の名だたる音楽家を何人も育てたことで知られる)に師事して、対位法を学ぶようアドバイスしました。「イルフォケブー “ストゥーディ”(study)」(学びなさい)。ラヴェルは少年に「にんじん」とニックネームをつけて呼んでいたそうです。少年の方も、ラヴェルの偉大さだけでなく、その人柄やダンディーさにも心を奪われたようで、ラヴェルの帰国後、フランスに手紙をたくさん書き送っていたといいます。

ストラビンスキーとナディア・ブーランジェ:
ブーランジェはアメリカやヨーロッパで主要なオーケストラを指揮した最初の女性。ストラビンスキー作品の世界初演も手がけている。
その後この少年は、作曲家デイヴィッド・ダイアモンド(1915年 – 2005年)として成功し、多くの管弦楽や室内楽のための楽曲を書いてアメリカの作曲家として名を成しました。同性愛者であることを当初から公表しており、それが音楽家としてのキャリアに響いたとも言われます。ラヴェルが亡くなった1937年には『Elegy in Memory of Ravel』のタイトルで、懐かしい師を偲ぶ曲を書きました。
8. ラヴェルの現代音楽講座 in America
サンフランシスコ、ロサンジェルス、ポートランド、ミネアポリス、カンサスシティなどをコンサートで回ったのち、4月6日、7日とラヴェルはテキサス州ヒューストンで、レクチャー+コンサートを行ないます。レクチャーについては、演奏のための1500ドル(現在の価値で約240万円)に加えて、500ドル(同80万円)が支払われました。レクチャーの原稿を書いたのは、ラヴェルの門弟で音楽学者のロラン・マニュエルだと言われています。ラヴェルの音楽に対する考えや志向をよく理解していた人物です。レクチャーではラヴェルがそれを元に話し、通訳が英語に訳しました。このレクチャーのショートバージョンは、ヒューストンより前のコンサートでも何回か発表されていました。

ロラン・マニュエル(左)とラヴェル(リヨン=ラ=フォレにて)。
ラヴェルはレクチャーで、現代音楽、中でもフランス音楽に焦点をあて、自分の作曲法もまじえてユニークな意見を展開しています。以下にレクチャーの内容の一部を紹介します。
ライス・インスティチュート(現在のライス大学)の招きによるレクチャーから
1928年4月6日、7日 スコティッシュ・ライト・カテドラルにて
<エリック・サティ(1866年 – 1925年)について>
サティは非常に鋭敏な知性の持ち主でした。ずば抜けて優秀な発明家の知性です。また偉大な実験精神の持ち主でもありました。サティの実験はリストが到達したレベルには至ってなかったとしても、多様性とその重要性において、計り知れないほどの価値をもたらしました。率直にして巧みな方法で、サティはこの道を示しましたが、他の音楽家たちが自分の敷いた道を追いかけはじめると、すぐに自身は方向を変え、ためらうことなく、新たな実験場へと道を切り開いていきました。そのようにしてサティは、新たな音楽の啓示を他の音楽家に与えつづけたのです。しかし彼自身は、おそらく、自分の発見を完成された作品に一つも使わなかったと思われます。それでも今日、サティがいなかったら生まれなかったであろうたくさんの作品を我々は手にしています。彼のもたらしたものはまったく独善的でなかったため、多くの音楽家へのかけがえのない価値ある贈り物になりました。
<クロード・ドビュッシー(1862年 – 1918年)について>
作曲家がもつ自らの国への意識は、作品を生み出す上で、大きな刺激となることがあります。たとえば、フランスの初期の作曲家たちによって示された客観性と明快なスタイルは、フランス音楽の歴史の中でもっとも影響力のある天才、ドビュッシーへの豊かな遺産となりました。これはドビュッシーがただの模倣者であることを意味するのでしょうか? 違います! ではドビュッシーの象徴主義(1880年代後半にフランスで起きた反写実主義的な芸術運動)、あるいは印象主義と呼ばれているものは、フランス的なものと敵対しているのでしょうか? まったく正反対です。なぜなら繊細でレースのような品の良いドビュッシーの作品の表面下に、フランス音楽特有の精密な様式をたやすく発見することができるからです。ドビュッシーの天才的な音楽性は、明らかに、自ら原理を生み出し、それを常に進化させ、自由に表現するという個人の資質によるものですが、そうであってもなお、フランスの伝統に対してある忠実さを保っています。ドビュッシーに対しては、音楽家としても人間としても、深い尊敬と賞賛の念をもっていますが、わたしと彼とでは、生来のものがまったく違っています。わたしが受け継いだものが、ドビュッシーとまったく関係ないとは思いませんが、わたしの初期の発展には、ガブリエル・フォーレ、エマニュエル・シャブリエ、エリック・サティの存在があります。また、あなたがたのお国の偉大な作家エドガー・アラン・ポーの美学は、わたしにとってかけがえのないものです。そしてマラルメの未完の詩集もそうです。(わたしがマラルメの象徴主義の作品に感服したとしても)、自分自身の音楽は、ドビュッシーの象徴主義とは正反対の方向へ進んでいることをいつも感じています。
<アルノルト・シェーンベルク(1874年 – 1951年)について>
ここ15年、20年の間、音楽家や批評家は、二つの潮流に大いなる関心を抱いてきました。それは無調と多調の音楽です。これについて激しい議論が起こり、無調音楽はどこにも行き着けない袋小路だ、という意見を耳にしたり、目にしたりもしました。しかしわたしはこの意見には妥当性がないと思います。それはシステムとしてはそうであっても、影響力においてはまったく当てはまらないからです。実際のところ、シェーンベルクは彼の支持者に圧倒的な影響力をもっています。彼の芸術の重要性は非常に捉えにくく、より繊細なものです。彼の芸術は音楽のシステムとしてではなく、美学として重要なのです。わたしの『マダガスカル島民の歌』はまったくシェーンベルク風ではありませんが、もし彼がああいった楽曲を書いていなかったら、わたしがこの作品を書けたかどうか定かではありません。

左:ラモン・カザスによるサティのポートレイト 。
中央:クロード・ドビュッシー。
右:シェーンベルク(オーストリア、パイエルバッハにて、1903年)。
<ドビュッシーとの類似性という指摘について>
わたしの音楽は、同時代の作曲家に大きな影響を与えた、としばしば言われてきました。中でもわたしの初期の作品『水の戯れ』(1901年)は、ドビュッシーの『雨の庭』(1903年)に影響を与えたと言われます。さらに驚くべきは、わたしの『ハバネラ』にも同じことが当てはまるなどと言われます。このような意見の正否については、他の者に判断を譲りたいと思います。とはいえ、コンセプトにおいてこの二者には非常に似たものがあり、それが互いの直接的な影響なしに、しかもほぼ同時期に、それぞれの意識の中で、熟成していったとしてもなんの不思議もありません。こういったケースでは、楽曲はたくさんの外見的な類似点を持ち得ますが、二人の作曲家の個性には、多くの違いが見いだされます。二者が自分の個性を探し求め、個別のものを発見してきた道のりを考えれば、いかなる人間も、すっかり同じということはありえないとわかるでしょう。もう一度言います、もし外面の類似性に気をとられ、似ていない異なる内面の表明を見失うことがあれば、二人のうちのどちらかが、盗作者のように見えてしまうということが起こります。
録音と楽譜:IMSLP
『水の戯れ』(Jeux d’eau)
http://imslp.org/wiki/Jeux_d’eau_(Ravel%2C_Maurice)
『雨の庭』(Jardins sous la pluie/Estampes)
http://imslp.org/wiki/Estampes_(Debussy,_Claude)
*録音はこのページの楽譜の下、「非商業録音」と書かれたところにあります。
このレクチャーの最後で、ラヴェルはアメリカ音楽の豊かさに触れ、中でもジャズやブルースといった黒人音楽が、(ヨーロッパの古典の流れを汲む)アメリカ音楽の創生に、大きな影響を与えていることを強調しています。
ヒューストンでのレクチャー&コンサートを終えたラヴェルは、10日間の休暇をとります。おそらく契約の中で明記されていたのでしょう。メキシコ湾に行き、車での小旅行にも出たようです。また鉄道でグランドキャニオンも訪問しています。実はヒューストンに着く1日前、コンサートはなかったのですが、ラヴェルのたっての希望でニューオリンズに寄っています。ニューオリンズ(「新オルレアン」の意味)は18世紀にフランス領だったため、ラヴェルはこの地のクレオール料理を味わいたかったこと、またジャズの発祥地にも興味があったと思われます。
それ以前にもアメリカツアー中、ジャズを聴くためだけの理由で、ラヴェルはオマハに立ち寄っています。デンバーからミシシッピーに向かう際、列車をわざわざ乗り換えてオマハまで行き、午後のひとときジャズを楽しんでから、夜の10時に目的地へと向かったそうです。
4月16日、グランドキャニオンをあとにしたラヴェルは、バッファロー、モントリオールとコンサートでまわり、4月21日の深夜、ニューヨークから定期船「パリ号」で帰途につきました。ラヴェルにとって、この演奏旅行は大金を稼ぐまたとないチャンスであったと同時に、アメリカの熱狂的な聴衆と出会ったり、口うるさい批評家たちに最新の「風変わりな」音楽を披露したり、とその名を世界に広めるきっかけをつくりました。1928年4月27日、ラヴェルはフランス北西部の港町ル・アーブルに到着しました。そのときの写真が以下のものです。